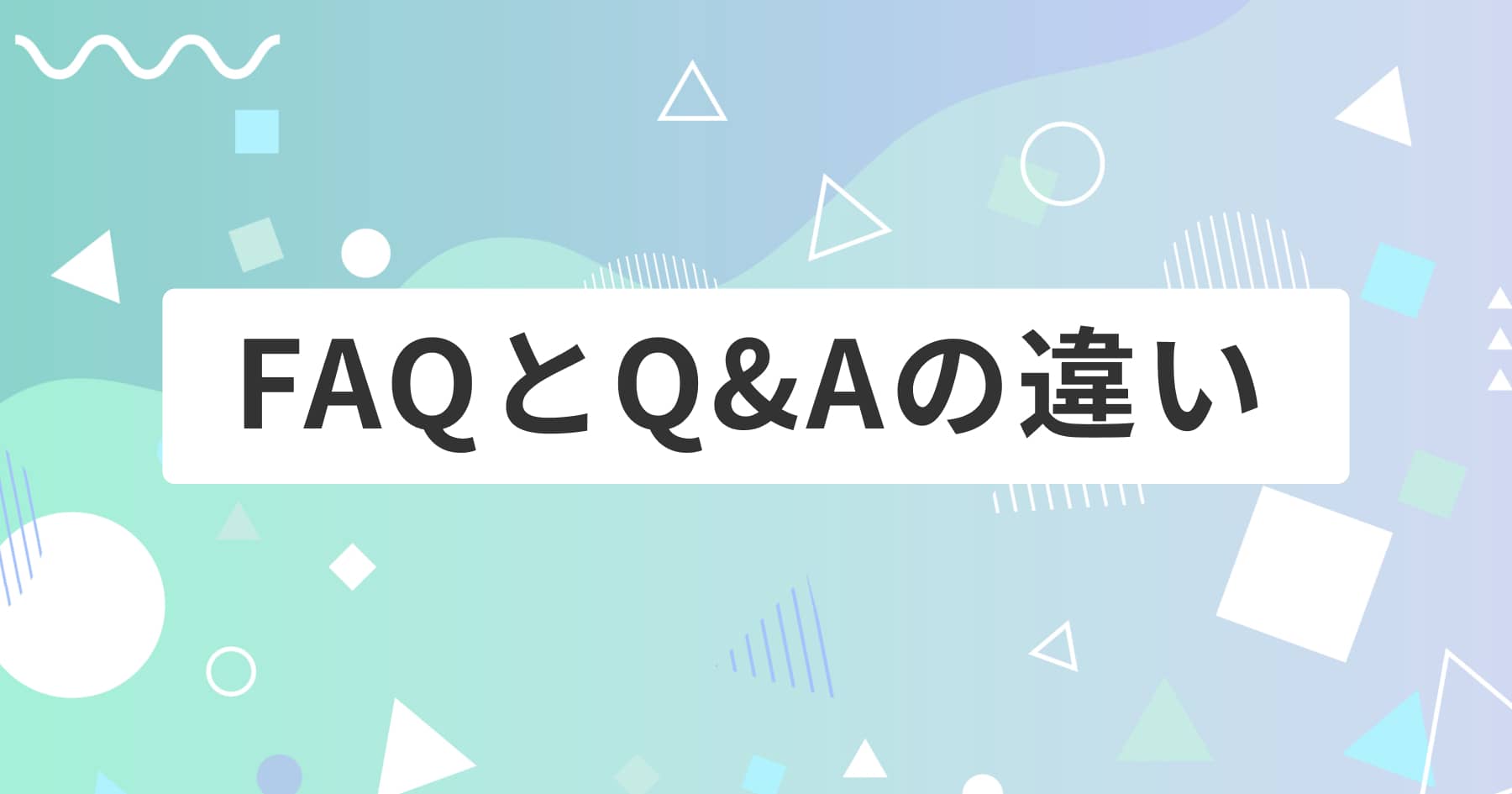
「FAQとQ&Aって同じじゃないの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
FAQ(よくある質問)とQ&A(質疑応答)は、似ているようで役割や活用方法が少し異なります。
本記事では、FAQとQ&Aの意味の違い、適切な使い分け方、作成ポイントを分かりやすく解説。
さらに、FAQの作成後に役立つAIチャットボットの併用方法まで紹介します。
「FAQとQ&Aの違いを知りたい」「どちらを用意すべきか迷っている」という方は、ぜひ最後までご覧ください!
「FAQ」と「Q&A」は、どちらも「質問と回答」をまとめたコンテンツとしてよく使われますが、実は意味や使われ方には違いがあります。
特に、企業のウェブサイトや社内ポータルで活用する際には、それぞれの役割を正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、FAQとQ&Aの意味や特徴を整理し、どのように使い分けるべきかを分かりやすく解説します。
FAQとは、「Frequently Asked Questions」の略で、日本語では「よくある質問」と訳されます。
ユーザーや従業員から頻繁に寄せられる質問をあらかじめ整理し、回答とセットで一覧化したものです。
FAQを用意することで、同じような問い合わせを繰り返し受ける負担を減らせるほか、ユーザー自身が疑問を自己解決できるようになるため、満足度向上および全体的な効率化につながります。
Q&Aは、「Questions and Answers」の略で、直訳すると「質問と回答」という意味です。
FAQと比べて、Q&Aはより柔軟に使われる言葉で、必ずしも「よくある質問」に限定されません。
例えば、イベントやセミナー後に参加者からの質問と回答をまとめたページや、製品詳細ページで個別に設置されたQ&Aコーナーなど、状況に応じて幅広く活用されています。
・FAQはよくある質問を回答とセットで一覧化したもの
・Q&Aは質問と回答という意味であり、よくある質問に限定されない
「FAQ」と「Q&A」は、どちらもユーザーの疑問を解消するための便利な仕組みですが、役割や使いどころには明確な違いがあります。
ここでは、FAQとQ&Aの役割の違い、効果的な使い分け方、そして具体的な活用事例を紹介します。
FAQの役割は、よくある質問を事前に整理し、同じ問い合わせが繰り返されるのを防ぐことです。
企業のウェブサイトやECサイト、社内ヘルプページなど、問い合わせ件数を減らしたい場面で大きな効果を発揮します。
一方で、Q&Aの役割は、より幅広い「質問と回答」を柔軟に提供することです。
FAQほど事前に整理されていなくても、必要に応じて最新の質問や個別の事例を含めて更新できる点が特徴です。
FAQとQ&Aを効果的に活用するには、以下のポイントを押さえましょう。
FAQを使うべきケース
・問い合わせが多く、同じ質問が繰り返される
・サイト訪問者が自己解決できる情報を整理したい
・社内ヘルプデスクの負担を減らしたい
Q&Aを使うべきケース
・イベントや説明会などで出た質問をまとめたい
・FAQに含めない詳細な質問や一時的な内容を公開したい
・個別の商品やサービスごとの細かな質問に答えたい
FAQの事例
例:ECサイトでの配送・返品・支払い方法など、購入者から頻繁に寄せられる質問を一覧化した「よくある質問」ページ。
Q&Aの事例
例:ウェビナー後に参加者からの質問を整理して、登壇者が回答を追記した「セミナーQ&Aページ」。
社内向けの新システム導入時に、従業員からの質問と回答を随時追加していく「Q&Aコーナー」など
・FAQは同じ質問が繰り返されることを防ぐ
・Q&AはFAQより柔軟に回答を提供することができる
「FAQ」と「Q&A」、どちらを用意すべきかは、自社が抱える課題や目的によって変わります。
ここでは、目的別の選び方と、両方を効果的に活用する併用例を紹介します。
問い合わせ対応を効率化したい場合
定型的で頻出する質問を減らすことが目的なら、まずはFAQの整備が最優先です。
代表的な質問と回答を分かりやすくまとめ、誰でも自己解決できる状態をつくりましょう。
また、社内の問い合わせ管理を効率化するためのツールを導入する場合にもFAQの整備は必須です。
ユーザーの多様な疑問をカバーしたい場合
FAQだけでは対応しきれない、より具体的な質問やイレギュラーな内容が多い場合はQ&Aの活用がおすすめです。
また、社内外で集まった質問を随時追加できるため、最新のニーズに合わせて情報を更新できます。
ケースに応じて、FAQとQ&Aを組み合わせて活用することもできます。
例えば、
・社内ポータルや社内のメンバーが情報を閲覧できる場所にFAQを掲示
・問い合わせフォームやチャットサポートで個別に寄せられた質問を、Q&Aとしてまとめて公開
という流れです。
また、FAQをAIチャットボットに連携させて回答を即時提供し、解決できなかった質問はQ&Aに蓄積していく方法も有効です。
これにより、ユーザーの自己解決率を高めつつ、最新の疑問をデータとして活かすことができます。
・問い合わせ対応の効率化が必要な場合はFAQの整備が必要
・Q&Aは個別対応やイレギュラー対応のためにデータとして蓄積しておくと有効
FAQを作るだけでは、ユーザーの自己解決率は上がりません。
「どの質問を載せるか」「どう書くか」「どう維持するか」が重要です。
ここでは、効果的なFAQを作るための3つのポイントを紹介します。
まずはユーザーがどんな質問をしているのか、正確に把握することが大切です。
・過去の問い合わせ履歴を分析する
メール、電話、チャットなど、顧客対応履歴を整理し、頻出する質問を抽出しましょう。
・現場の担当者にヒアリングする
情シスや総務、カスタマーサポート担当など、問い合わせ者と接点のある部署から情報を集めると、現場感のある質問を把握できます。
・ユーザーアンケートを実施する
直接ユーザーに「困ったこと」「知りたいこと」をアンケートで聞く方法も効果的です。
こうして集めた質問をカテゴリーごとに整理し、重複をまとめてFAQの原案を作成します。
FAQを作成する際に、社内の専門用語や内部事情をそのまま書いてしまうことがよくあります。
しかし、読むのはユーザーです。分かりやすく、シンプルにまとめましょう。
・質問はユーザー視点の言葉で書く
専門用語を避け、ユーザーが検索しそうなキーワードを盛り込むのがポイントです。
・回答は結論ファーストで
長文になりすぎず、最初に結論を示し、その後に詳細を補足します。
・図解やリンクで補足する
必要に応じて画像や関連ページへのリンクを入れると、理解度が高まります。
FAQは作った時点で完成ではなく、運用してこそ意味があります。
・定期的に内容を見直す
社内の規約やルール、資料、マニュアルなどの変更に合わせて、古い情報を更新しましょう。
・新しい質問を追加する
FAQで解決できなかった質問は、Q&Aやチャット履歴を元に随時FAQに追加します。
・効果を分析する
FAQページの閲覧数や問い合わせ件数をモニタリングし、改善点を見つけましょう。
・ユーザーの質問を正確に把握してFAQの原案を作成する
・FAQはユーザー視点で書き、継続的にメンテナンスを行う
FAQページを用意していても、「探しにくい」「読むのが面倒」という理由で、ユーザーが必要な情報にたどり着けないことは少なくありません。
そんな時に役立つのが、FAQと連携して自動応答するAIチャットボットです。
どれだけ充実したFAQページを作っても、
・質問の数が多くて探しにくい
・ページ内を検索しても求める回答がヒットしない
・文章を読むのが面倒
といった理由で、ユーザーが自己解決できず、結局問い合わせにつながってしまうことがあります。
特にモバイル環境では、長いページをスクロールして探すのは大きな負担です。
AIチャットボットを導入すれば、ユーザーは欲しい回答を「探す」のではなく「聞くだけ」で済みます。
・ユーザーがチャットで質問を入力する
・チャットボットがFAQデータベースを検索して、最適な回答を提示する
・必要に応じて追加情報を案内する
この仕組みを使えば、FAQの情報を最大限に活用しながら、問い合わせ対応を自動化できます。
最近では、生成AIを活用したチャットボットが、より自然な会話でサポートしてくれるケースも増えています。
SlackやMicrosoft Teams
すでに社内に導入されているツールを窓口としながら社内の質問対応を自動化することで、情シスや人事などの負担を軽減できます。さらに、ユーザーにとっても負担が少ないです。
Webサイトのチャットウィジェット
ECサイトなどの場合は、サイトのチャットウィジェットなどに設置することで顧客からの問い合わせ対応を24時間自動化し、カスタマーサポートのコストを削減できます。
helpmeee! KEIKOなどのAIチャットボットを活用すれば、ビジネスチャットや外部ツールと柔軟に連携できるので、導入の負担も導入後に利用するユーザーの負担も軽減し、スムーズに利用を開始することができるためおすすめです。
・FAQだけでは探すのが面倒で利用されなくなることも多い
・FAQはAIチャットボットと連携することでユーザーの負担が大幅減
FAQとQ&Aは似ているようで役割が異なり、目的に合わせた使い分けが大切です。
FAQを作る際は、ユーザー視点で内容を整理し、定期的な更新を忘れないことがポイントです。
さらに、AIチャットボットと連携することで、ユーザーが欲しい情報をスムーズに届けられ、問い合わせ対応の効率化にもつながります。
効率的な情報提供でユーザー満足度を高め、業務負担を減らすために、FAQとAIチャットボットをぜひ活用してみてください。